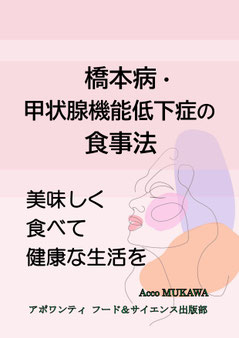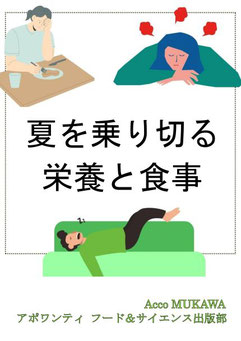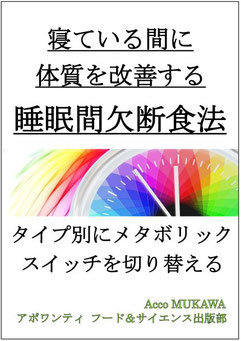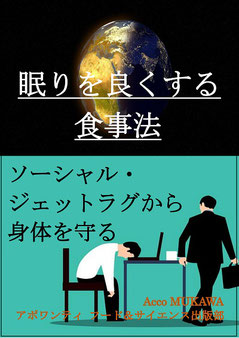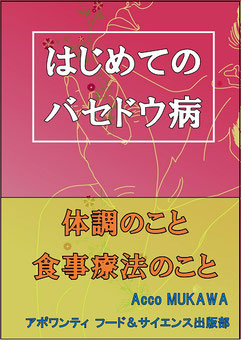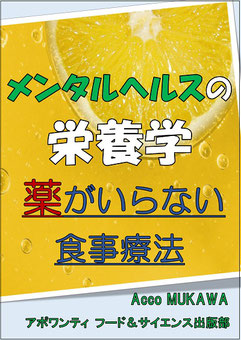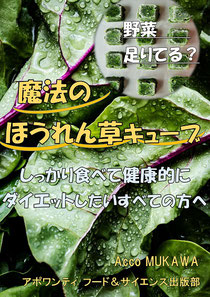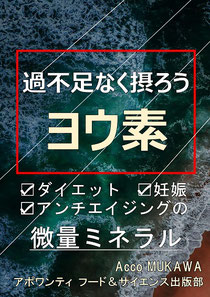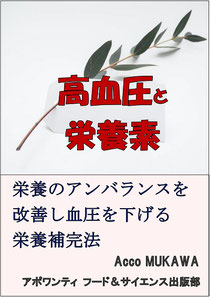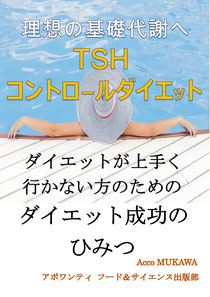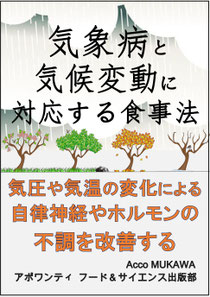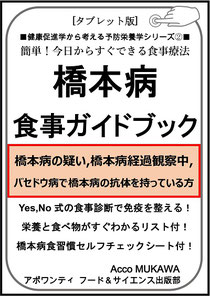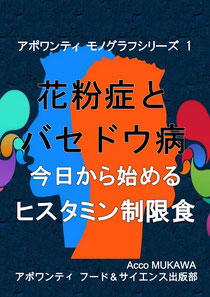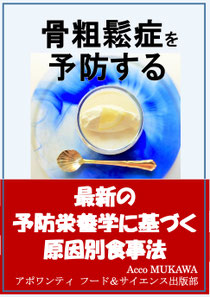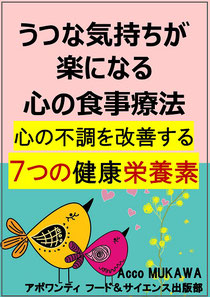内分泌かく乱物質とは、体内に取り込まれることでホルモンと似た作用をしたり、ホルモンの働きを阻害したりする化学物質のことを指します。これにより、ホルモンの分泌や作用が乱れ、内分泌系の正常な機能が妨げられる可能性があります。
特に、甲状腺ホルモンも内分泌かく乱物質の影響を受ける恐れがあると考えられています。本記事では、内分泌かく乱物質の基本的な仕組みと、甲状腺機能に及ぼす影響について解説します。
内分泌とは
内分泌とは、生命活動を調整するホルモンを血液中に分泌する仕組みのことです。ホルモンはごく微量で体内の恒常性を維持する重要な役割を果たします。代表的なホルモンには以下のようなものがあります。
- 甲状腺ホルモン(エネルギー代謝や成長を調整)
- エストロゲン(女性ホルモン、月経や妊娠に関与)
- インスリン(血糖値の調整)
これらのホルモンが適切に機能することで、体のバランスが維持されています。しかし、内分泌かく乱物質が体内に取り込まれると、このバランスが崩れる可能性があります。
環境ホルモンとは?
「環境ホルモン」という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。これは、内分泌かく乱物質を指す一般的な呼称であり、環境中に存在するホルモン作用を持つ化学物質を指します。
代表的な内分泌かく乱物質
環境ホルモン(内分泌かく乱物質)にはどのようなものがあるのでしょうか。
65種類が内分泌かく乱物質として疑われていますが、ここでは一例をあげます。
現在、約65種類の化学物質が内分泌かく乱物質として疑われています。以下に代表的なものを挙げます。
- PCB(ポリ塩化ビフェニール)
- PBB(ポリ臭化ビフェニール)
- ビスフェノールA(プラスチック製品に含まれる)
- フタル酸エステル(プラスチックの可塑剤)
- PFAS(有機フッ素化合物)
- ダイオキシン(焼却時に発生)
- チオシアン酸塩
- 硝酸塩・亜硝酸塩(食品や水に含まれる)
- カドミウム、鉛、水銀(重金属汚染)
これらの物質は食品、飲料水、空気、化粧品、プラスチック製品など、日常生活のさまざまな場面で暴露する可能性があります。
内分泌かく乱物質の影響
ホルモンは特定の受容体と結合することで作用を発揮しますが、内分泌かく乱物質はこの仕組みを妨害することが問題となります。
- ホルモンの生成を阻害(甲状腺ホルモンの生成低下)
- ホルモン受容体に結合し、本来のホルモンの働きを妨害
- ホルモンの分解を早める、または遅らせる
- ホルモンを運搬するタンパク質に結びつく
これにより、甲状腺ホルモンの適切な調整ができなくなり、甲状腺機能低下症や自己免疫疾患(例:橋本病)と関連する可能性が指摘されています。
甲状腺ホルモンへの影響
近年の研究では、内分泌かく乱物質が甲状腺機能を低下させる可能性が示唆されています。特に、
- ビスフェノールA(BPA)(プラスチック容器や缶詰の内部コーティングなど)
- PFAS(フライパンのコーティングや防水加工品、井戸水など)※
- 重金属(鉛・水銀)(汚染されたマグロをはじめとする魚介類など)
などの報告があります。ただし、科学的な因果関係は完全には解明されていません。
対策とまとめ
現在、日本をはじめ世界中で内分泌かく乱物質の影響を調査し、その作用メカニズムや毒性評価を進めています。
橋本病・甲状腺機能低下症の原因は多様で、環境ホルモンの影響はその1つの可能性にすぎません。そのため過度に心配する必要はありませんが、日常生活で甲状腺の健康を守る工夫として、できることを取り入れていきましょう。
- プラスチック製品(特にBPAを含むもの)の使用を減らす
- 食品添加物や残留農薬に注意する(加工肉を食べ過ぎない、野菜は良く洗ってから使用する)
- 飲料水に注意する※
- 重金属汚染のリスクがある魚介類の過剰摂取を避ける
科学的な知見が進む中で、より安全な生活環境を整えていくことが重要です。