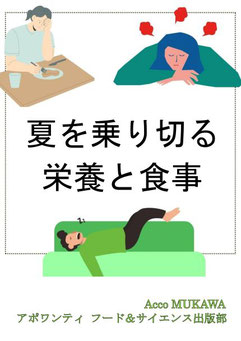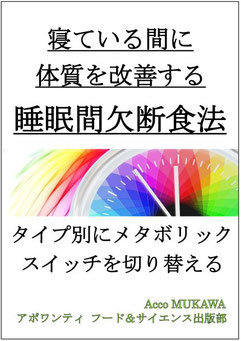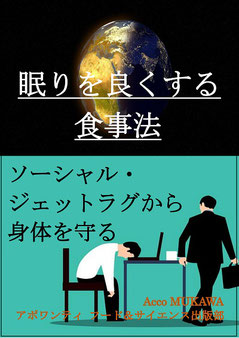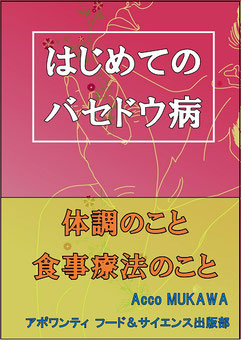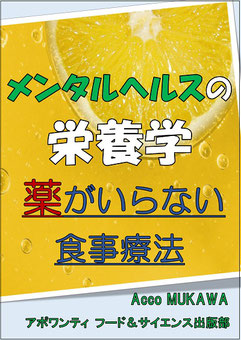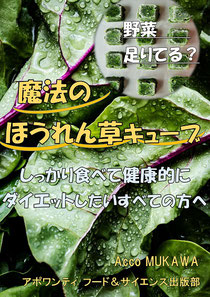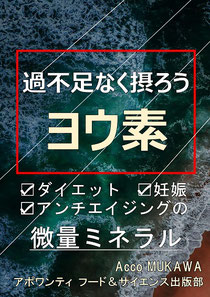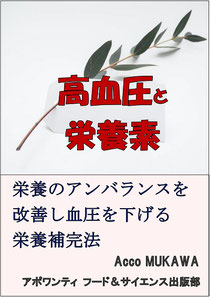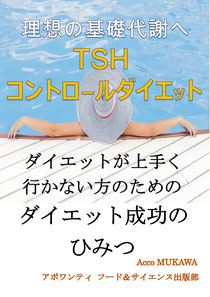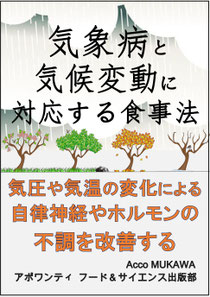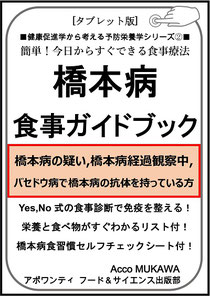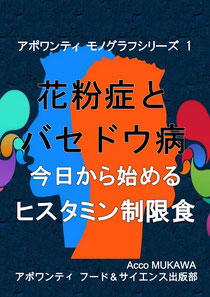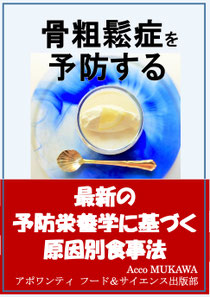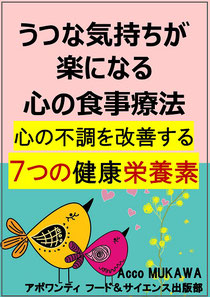橋本病やバセドウ病を持つ方は、1型糖尿病や2型糖尿病のリスクが高まることが知られています。本記事では、橋本病や甲状腺機能低下症が糖尿病とどのように関係するのか、またその対策について詳しく解説します。
甲状腺機能低下症と糖尿病リスクの関係
橋本病や甲状腺機能低下症をきっかけに2型糖尿病が発見されるケースや、その逆に2型糖尿病の治療中に橋本病が診断されるケースもあります。また、もともと糖尿病を持つ方は、橋本病によって血糖コントロールが悪化する可能性があるため注意が必要です。
その主な原因として、甲状腺ホルモンの低下によりインスリンの分泌が遅れることが挙げられます。インスリンは血糖値を下げる働きをするホルモンですが、甲状腺機能が低下すると、食後の血糖値を適切に下げることができず、結果として2型糖尿病のリスクが上昇します。
さらに、甲状腺機能低下症ではインスリン抵抗性が増大することもあります。これは、インスリンが分泌されても十分に作用しなくなる状態であり、血糖値の管理を困難にします。
消化管からの糖吸収の遅延と血糖コントロールへの影響
甲状腺ホルモンは、消化管の運動や栄養素の吸収にも影響を与えます。甲状腺機能が低下すると、食べた糖の吸収も遅れることがあります。一見すると血糖値の急上昇を防ぐように思われますが、これは食後の血糖コントロールを不安定にする要因にもなります。なぜなら、糖の吸収が遅れることでインスリンの分泌とタイミングが合わず、結果的に食後高血糖や血糖値の乱高下が生じる可能性があるからです。
経過観察中の橋本病(潜在性甲状腺機能低下症)と糖尿病
甲状腺ホルモンの低下が軽度な場合でも、インスリンの分泌が遅れることがあり、糖尿病のリスクは無視できません。特に、橋本病が進行しないように経過観察中の方でも、血糖値の変動には注意が必要です。
肥満や痩せ型とインスリン抵抗性の増大
肥満はインスリン抵抗性を増大させる要因として知られていますが、最近の研究では、痩せ型でも「隠れ肥満」と呼ばれる状態の人はインスリン抵抗性が高くなり、糖尿病のリスクが増すことが示されています。特に、橋本病による代謝低下がある場合、適正な体重管理がより重要になります。
糖尿病リスクを下げるための3つの対策
① 食生活の改善
- 糖質の過剰摂取を避け、食物繊維をしっかり摂ることで血糖値の上昇を緩やかにする
- 栄養バランスの良い食事を心がける
② 適度な運動習慣の継続
- 筋肉を使うことでインスリンの感受性を向上させ、血糖値のコントロールを助ける
- 有酸素運動と筋力トレーニングをバランスよく取り入れる
③ 適正体重の維持
肥満だけでなく、過度な痩せすぎも血糖値管理に影響を及ぼすため、健康的な体重を維持する
1型糖尿病と橋本病の関連
1型糖尿病と橋本病、バセドウ病を併発するケースもあり、1型糖尿病の患者では自己抗体の一種である抗GAD抗体(抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体)の陽性率が高くなることが報告されています。このような自己免疫疾患の関連性を理解し、早期の診断と適切な管理が重要です。
まとめ
橋本病や甲状腺機能低下症は、糖尿病の発症や悪化に関与することが明らかになっています。甲状腺ホルモンが低下すると、インスリン分泌の遅れやインスリン抵抗性の増大が起こり、糖尿病リスクが高まります。さらに、消化管の働きが遅れることで糖の吸収が不安定になり、血糖コントロールが難しくなる場合もあります。
そのため、バランスの取れた食事、運動習慣の確立、適正体重の維持が、糖尿病リスクを抑えるための重要なポイントとなります。自身の体調をよく観察しながら、適切な対応をしていくことが大切です。
参考文献
Chaker L, Bianco AC, Jonklaas J, Peeters RP. Hypothyroidism. Lancet. 2017 Sep 23;390(10101):1550-1562. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30703-1. Epub 2017 Mar 20.
Sato M, Tamura Y, Nakagata T, Someya Y, Kaga H, Yamasaki N, Kiya M, Kadowaki S, Sugimoto
D, Satoh H,
Kawamori R, Watada H. Prevalence and Features of Impaired Glucose Tolerance in Young Underweight Japanese Women. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Apr 23;106(5):e2053-e2062. doi:
10.1210/clinem/dgab052.